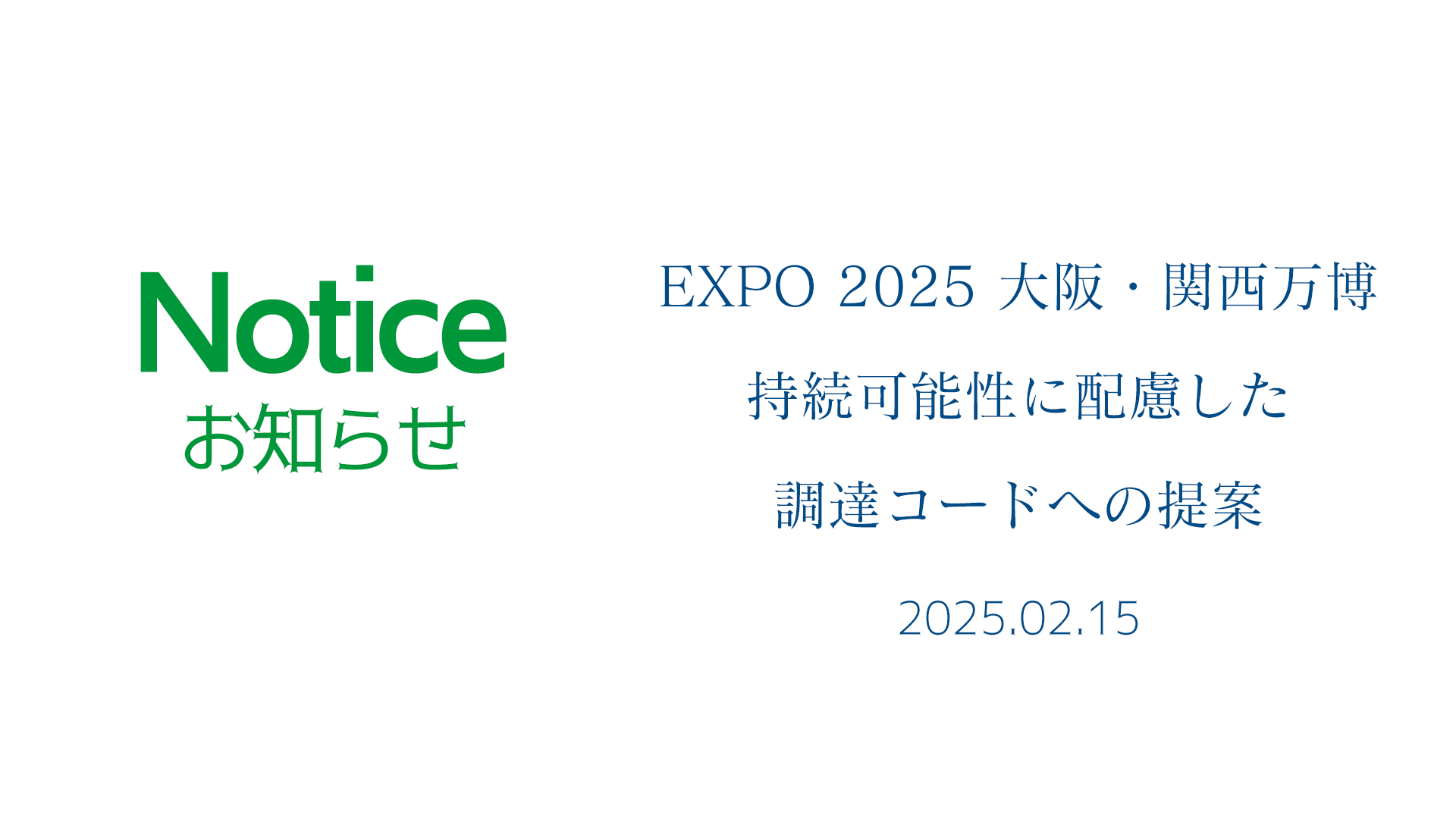SDGS万博市民アクション 持続可能な調達分科会
ウータン・森と生活を考える会
NPO法人AMネット
一般社団法人 熱帯林行動ネットワーク(JATAN)
持続可能性に配慮した調達コードの現状
- 調達コードの個別基準「木材」「紙」におけるFSC認証とPEFC認証/SGEC認証、また「パーム油」におけるRSPO 認証とMSPO認証及びISPO認証には、認証基準の厳しさに大きな差があると認識している。
- また、FSC認証の内訳(FSC100%、FSCミックス、FSCリサイクル等)や、RSPOの内訳(IP、SG、MB(マス・バランス))にも大きな差がある。
- 持続可能性の確保に向けた取組状況についてのチェックシート(https://www.expo2025.or.jp/wp/wpcontent/uploads/221212_02_07_jizokukanouseichecksheet.xlsx )の【該当する認証や確認の方法】(木材、紙)では、「FSC,PEFC/SGEC」と「その他」のチェック欄が設けられているが、FSCかPEFCかはチェックできない。
- パーム油を原料に含む揚げ油・石鹸洗剤を調達する場合は、協会HPに公表されている調達計画書に認証名を含めて記載することとしており、協会では認証名を確認することとしているとのことだが、RSPOの内訳などは示されていない。
- チェックシートをFSCかPEFCかを明確に区別し、途中経過報告および最終報告で公表することが求められる。
- 「木材」「紙」「パーム油」について、製材所所在国・地域を選ぶ必要があるが、原材料の調達地は記載が求められていない。
- 2次、3次以降のサプライチェーンについては記載を求めていない。なお、協会が個別に確認が必要と判断した時には事業者に確認することとしている。
- 選定業者のみヒアリングシートによるヒアリングをするとしているが、ヒアリングシートは公開されていない。
持続可能性に配慮した調達コードの具体的な問題点①PEFCの問題
- 上記の理由として、調達コード担当者は、調達コードの個別基準(https://www.expo2025.or.jp/overview/sustainability/sus-code/ )のうち、例えば「木材」「紙」では、持続可能性の観点から要件①~⑤を規定し、FSC、PEFC、SGECの認証材(認証紙)は①~⑤への適合度が高いと説明している。
- 上記 1 の木材について、持続可能性の観点から以下の①~⑤が求められる。なお、サプライヤーはコンクリート型枠合板については再使用の促進に努め、再使用する場合でも①~⑤を満たすことを目指し、少なくとも①は確保されなければならない。
- 伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令等に照ら して手続きが適切になされたものであること
- 中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されている森林に由来するものであるこ と
- 伐採に当たって、生態系が保全され、泥炭地や天然林を含む環境上重要な地域が適 切に保全されており、また、森林の農地等への転換に由来するものでないこと
- 森林の利用に当たって、先住民族や地域住民の権利が尊重され、事前の十分な情報 提供に基づく、自由意思による合意形成が図られていること
- 伐採に従事する労働者の労働安全・衛生対策が適切に取られていること
- 再使用の促進に努めることは評価できる。しかし、熱帯林行動ネットワーク(JATAN)のニュース「遺漏の認証制度-サムリン社の汚れた木材を隠蔽し、国際市場を欺く森林認証の実態」https://jatan.org/archives/8818 によれば、マレーシア・サラワク州の木材大手サムリン社が管理し、PEFC森林認証プログラムの相互認証プログラムであるマレーシア木材認証制度(MTCS: Malaysian Timber Certification Scheme)によって認証された伐採事業には、重大な欠陥があることが分析によって明らかになった。
- 記事の内容によれば、木材大手のサムリン社が先住民コミュニティと大きな対立を起こし、環境破壊行為を繰り返しているにもかかわらず、マレーシアのサラワク州における同社の伐採事業は、MTCSによって「持続可能」であると認証され続けている。これにより、サムリン社の木材製品は、PEFC森林認証プログラムのグリーン材ラベルのもと、国際市場で販売されている。
- このことは、以下に違反している。
- ① 伐採・採取に当たって、原木等の生産された国又は地域における森林その他の採取地に関する法令等に照らして手続きが適切になされたものであること。
- ④ 森林の利用に当たって、先住民族や地域住民の権利が尊重され、事前の十分な情報提供に基づく、自由意思による合意形成が図られていること
- よって、「PEFC、SGECの認証材(認証紙)は①~⑤への適合度が高い」ことは誤りである。
持続可能性に配慮した調達コードの具体的な問題点②PEFCとFSCの違い
- インドネシアのアジア・パルプ・アンド・ペーパー (APP)社は、日本との取引も多い製紙メーカーである。APP社と、同じくインドネシア製紙メーカー大手のAPRIL社とともに、FSC認証から絶縁措置を取られた状態である。https://connect.fsc.org/current-cases/policy-association-cases/asia-pulp-and-paper-app
- FSC は、APP社が破壊的な森林管理行為に関与しており、そのため提携方針に違反しているという大量の公開情報があったため、2007 年 10 月に同社との関係を解消した。その後、APP社がFSCシステムへの復帰に関心を示し、広範な利害関係者の関与を経て、離脱終了に向けたロードマップが策定されたが、APP との離脱終了に向けたロードマップを最終決定するプロセスはFSCにより一時停止されている。
- 一方で、APP社はPEFC認証を取得している。
- よって、FSC認証とPEFC認証を同等の認証とみなすことはできない。
持続可能性に配慮した調達のための提案
- サプライチェーンの2次、3次以降を含む生産国を全て記載すること。
- 認証を取得していない場合には、どのような形式で確認したのかの基準を公表するとともに、認証製品を含めて、調達方針毎に、全体の調達材の量と割合について情報開示する。
- 調達商品が取得していた認証の内訳(FSC100%、FSC ミックス、FSC リサイクル、PEFC、ISPO、MSPO、RSPOのIP、SG、MB等)を明確にするとともに、割合を含めて公表すること。また、その生産国も併記すること。
- 事業者のヒアリングシートをウェブサイト上に公開すること。ヒアリングシートに、調達方針の遵守の確認方法や利用量、調達先の生産国などを表記を追加すること。
- 上記の進捗状況(調達産品毎に、確認方法別に利用量、調達先国名などを情報開示)を持続可能な調達ワーキンググループに適宜報告し、調達コードに適合しているのかどうかを議論、結果を随時ウェブサイトなどに公表すること。
- 今後の国内外での国際的なイベントに活かされるような提言や最終報告書を終了後速やかに発行すること。
- 最終報告書をもとに、事業者や自治体、NGOなどを交えた公開報告会の場を設けること。
博覧会協会に以下提案を送付するとともに、報道各社にプレスリリースしました。